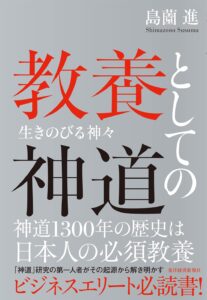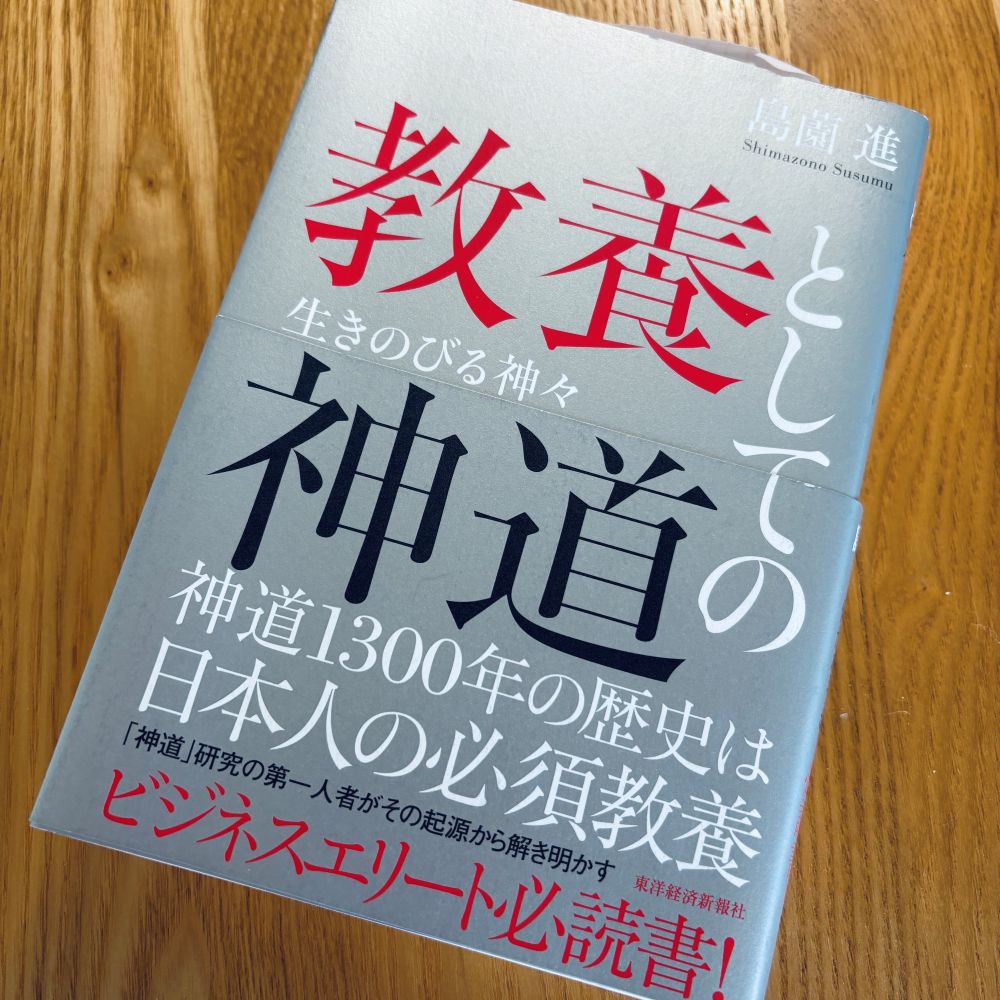
2025年8月読了
私は、筋肉少女帯「僕の宗教へようこそ」が大好きだ。
宗教という言葉を聞くだけで、このイントロが流れてきて、一日中脳内再生されるくらいにだ。
そんな私が手に取ったのは、宗教学者の島薗進先生の「教養としての神道」である。
もともと日本の古い不思議な話が大好きなので、過去のブックレビューを見てもらえれば、その一面もご理解いただけるのではないかと思う。
そうそう!昨年10月クールに放送されたドラマ「全領域異常解決室」にもすっかりハマってしまい、続編に期待している。
ということで以前から気になっていた、宗教や神道について、一般的な教養くらいは身に着けておきたいと思い手に取った。というわけだ。
神道といえば「古事記」「日本書紀」にある日本の神様の物語から始まり、果ては新興宗教団体やスピリチュアル、さらには教育勅語といった思想的なところにまで繋がっているよな…というくらいのなんとなくな感覚は持っていた。
本書はそれらを完全に網羅した一冊。神道の起源から始まり、縄文時代や「古事記」「日本書記」が編纂された時代背景を学び、仏教の到来によって習合したり、分離したり、三重と島根で喧嘩してみたり、政治と教育と混ざったり…。
その中で率直に思ったことは、宗教と政治と教育と混ぜたら危険だなということである。
個人的に興味深かったのは「布帛」についての記述だ。
ファッション業界の人であれば織物を「布帛」と呼ぶけれど、まさか日本の古代の祭祀において、神様へ布を箱に入れて捧げることを「布帛」ということを知り驚いた。確かに「日本書紀」では天照大神は機織りをしている記述があるし、当時の人々にとっては神様に捧げるほどに大切なものだったであろう。
本書とは関係ないが、いま個人的に気になっていることの一つが「織物の出現」だ。
実は未だに解明されていないミステリーだそうで、そもそも「服」は、いつ、誰が着始めたんだ?ということなのだ。古代人は獣の皮で服を作っていたわけで、いつから何をきっかけに糸を紡ぎ、布を織るようになるったんだ?って気にならないか?
いや、気になるのは私だけなのか?
ということで、神道についてフラットな目線で学ぶことができるので、ビジネスエリートを目指すのであればぜひ。ちなみに、私はビジネスエリートになりたい!
というのは置いといて。
神道の歴史を知ることで、宗教との距離感、戦前戦後の神道と政治・教育の関わり方など、あらためて考えることができた。戦後80年の今年にこれを読んでおいて本当に良かった。
では最後の曲です。